 |
 |
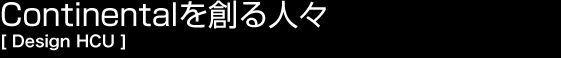 |
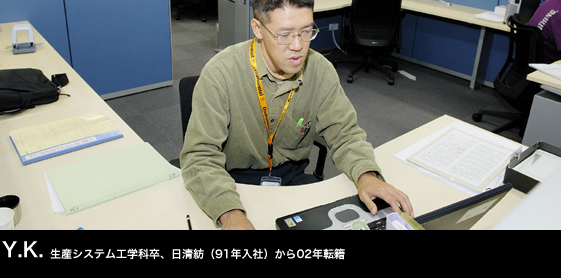 |
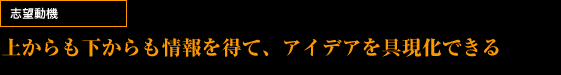 |
 |
 |
私は沼津高専から豊橋技科大の生産システムに進みました。もともとは機械系でしたが、コンピュータも扱いたいと思い、両方の要素がある研究室に入りました。大学時代の「ダイカスト金型内溶湯流れ解析」という研究テーマは、自動車業界の鋳物工程の最適化を目指すもので、縁があったし強い関心も持っていました。
カーメーカーへ就職という道もあったのですが、私は別のことを考えていました。カーメーカーの開発ではどうしても「上から下の目線」で部品メーカーを見てしまうと思ったからです。エンジニアとしての自分のキャリアを考えると、それは偏っているように思えたのです。そこでブレーキメーカーであるコンティネンタルを志望したのです。ブレーキ開発は、上(カーメーカー)からの依頼で開発しますが、そのときに下(ブレーキ部品、材料メーカー)の協力を求めます。
|
私はそういう立場の開発エンジニアを目指していたのですが、まさに予想通りでした。上からも下からも多くの情報を得ながら、自分のアイデアを具現化できる、それがコンティネンタルのエンジニアなのです。 |
 |
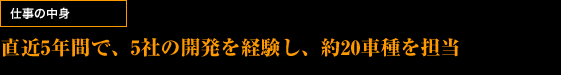 |
私の部署名はHCU。Hydraulic Control Unitの略で油圧制御ユニットです。クルマのブレーキは、ブレーキオイルの入ったポンプがあり、それをソレノイドバルブ(電磁弁)で押し出す構造です。昔のブレーキは、オン・オフの単純なものでしたが、現在はオイルの流量を制御するエレガントなメカニズムになっています。理想は無段階制御ですね。
この設計が私の仕事です。コンティネンタルは国内全メーカーのブレーキを開発製造していますが、私自身の直近5年間で言えば、チーム メンバーと共に5社の開発に携わり、約20車種のHCUを世に送り出したということになりますね。やはりそのクルマが注目されると本当にうれしいです。
一方で戸惑うこともあります。コンティネンタルは世界企業ですが、ヨーロッパと日本のカーメーカーの文化は違います。クルマに対する哲学の違いといってもいいかもしれませんね。
|
 |
 |
例えばクルマの水没。ヨーロッパでは水没したクルマは廃車扱いですが、日本では完全水没した場合でも、その後のブレーキユニットの性能について説明が求められます。ところが欧州では、なぜそんなことが必要なのか?と聞かれることがあります。こうした文化の違いは、グローバルに展開しているコンティネンタルならでは味わえる貴重な国際感覚の1つになると思います。 |
 |
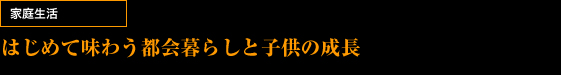 |
これまでの人生を振り返ると、清水市(現・静岡市)に生まれ、沼津高専、豊橋技科大、コンティネンタル浜北工場、旭R&Dセンター、そして2007年からの横浜開発センター。よく考えると実は都会で暮らすのははじめてなんですね。
現在、家族と一緒に都会暮らしを味わっている毎日です。その家族は妻と子供が3人。一番上は小学校3年の男の子、次は5歳の女の子、一番下の娘は2歳。休日はそのやんちゃな子供たちの相手をして過ぎていくことが多いですね。横浜は意外と公園が多く子供たちとちょっとした公園探索を楽しんでいます。また年に一回はワンボックスカーでキャンプに出かけたりもします。私が釣り好きなこともあって、山梨県の釣りスポットのあるキャンプ場に出かけることが多いですね。 |
 |
|