 |
 |
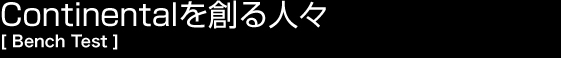 |
 |
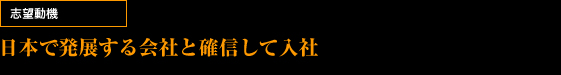 |
 |
 |
学生時代の研究テーマは「離散的な構造を持つ立体データの高速な図形処理アルゴリズム」。簡単に言うと、ある仮想空間に散りばめられた無数の点からオブジェクト(物体)をいかに実際の表現に近づけ、高速に描写することが出来るかというプログラム作りです。そんな研究をしていたこともあり、就職活動では自分の興味と研究が生かせる業種として、自動車とITを中心に活動していました。
そしてそんな中でコンティネンタルに出会ったのです。日本ではあまり知られていないけどヨーロッパでは非常に大きな会社であること、自動車産業ではブレーキ技術が重要になっていてアメリカでも数年後にESC搭載が義務づけられるということを聞き、まさにコンティネンタルはこれから日本で発展する企業だと確信して入社したのです。 |
|
 |
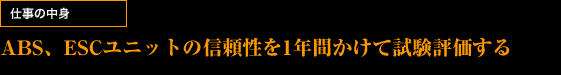 |
EBSユニットのテストは、いくつもの専門チームに分かれていますが、私の担当は台上評価、信頼性の評価です。テスト環境は過酷で、マイナス40℃からプラス110℃の温度環境でテストします。マイナス40℃になるとブレーキフルードはかなりドロドロ状態、逆にプラス110℃になるとさらさら状態。どちらの温度でも正常に動作しなくてはなりません。
皆さんの中にもロボットなどの機械を組み立てた経験をしている方も少なくないと思いますが、私たちも最初は試験装置を組んでからテストが始まります。試験装置を組んでユニットをセットし、どのような条件をかけてやるかを立案してスタート。試験期間は1年間に及びます。どういう条件をかけたときに、各輪の液圧がどのように作動しているのかをチェックしていくのです。その挙動は百態百様。本当に気の抜けない業務です。
規模は違いますが、ロケットやスペースシャトルの打ち上げに先立って、メカの信頼性テストが行われるのと同じようなイメージですかね。
|
 |
 |
私自身は入社して1年間は先輩について業務を覚えていましたが、2007年4月に独り立ち。今は1人で計画してテストを実行しています。しかし一人前かというとそうではありません(苦笑)。先輩を見ていて自分との違いをよく考えるのですが、一番大きな違いは、私が1方向からしか考えられない単一モードなのに対し、先輩は複数視点で問題を見て解決していくということです。この複数視点を身につけるにはまだまだ経験が必要だと思います。 |
 |
 |
私の土日の過ごし方はいたってシンプルですね。土曜日は映画鑑賞。これは大学生時代から続いている趣味です。
日曜日はクルマいじりとドライブ。20歳で免許を取ってから国産の一般的なコンパクトカーに乗っていたのですが、2007年8月に90年式のMR2を譲ってもらい、今はこれに夢中です。足回りを自分の好みにセットし、オイル交換も自分でやりますし、インテリアも自作です。もちろん古いクルマなので、ABS、ESCというようなブレーキ技術は使われていないのですが、逆にクルマの構造を理解するために非常にわかりやすく、業務にも役立っていると思いますね。 |
 |
|