 |
 |
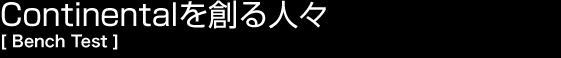 |
 |
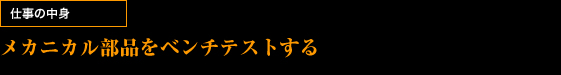 |
 |
 |
私の所属する部署「HECUベンチテストグループ」と聞いても、わかる人はいないでしょう。まずHECUとはHydraulic Electronic Control Unitの略。Hydraulic は「水力学の」「水(油)圧の」「液圧の」というような意味で、HECUは液圧(油圧)を電気的に制御する装置を指します。
製品は設計を経て試作されますが、その段階で「市場で通用するかどうかの台上テスト」を行います。だからベンチ(台上)テストと呼ばれるのです。
どんなテストをするのかというと、メカニカル部品の機能仕様を満足しているか、耐久性はどうか、強度は十分か、耐候性は? とテストしていくのです。 |
このベンチテストで、メカニカル部品の制御装置を確認してから、次のソフト実装、実車テストという段階を経て、いよいよ量産準備という段階に入るのです。
ブレーキという部品の開発と生産までに、こんなに多くの工程があると知らないと思いますが、クルマの安全を保証する基幹部品なので、その性能や信頼性を確認するベンチテストはとても重要な工程です。 |
 |
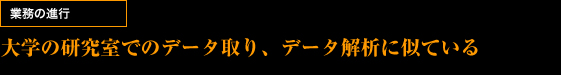 |
ベンチテストがどういう仕事かというと、大学の研究室と似ているかも知れません。コツコツとデータを取っていき、そのデータを解析して意味を読み取ります。大学でも機械科ならモータを回しっぱなしにして耐久試験をしたり、化学なら反応の進行具合のデータを取っていきますよね。それと似ていると思います。
ただし、私たちのベンチテストは製品として世に出ていい性能や信頼性を持っているのかどうかをテストしているので、大学での実験よりもはるかに多くの時間を費やしますし、非常に重要な任務です。
ベンチテストグループは複数のチームに分かれており、それぞれが違う自動車メーカーを担当しています。自動車メーカーは常時数年後に発売される複数車種の開発を進行させているので、1チームで複数のプロジェクトの製品評価を行っています。
プロジェクトによってベンチテストの進行状況はさまざま。とはいえ設備は限られているので、チームが互いに協力し合いながら業務を進めています。
|
 |
 |
|
 |
 |
大学では機械工学を専攻し、有限要素法を用いた応力解析をしていました。入社動機はとてもシンプルで「モノ作りに携わりたい」「動きのある部品がいい」というものでした。また大学での勉強は実社会ではあまり役立たないという人もいますが、私の場合、機械の知識はメカニズムを理解、考察する上で非常に役立っています。
これからはさまざまな機構のブレーキが増えてくると思います。そうなると性能や耐久性、信頼性のベンチテストの手法は変わるでしょうが、仕事の本質は変わらないと思います。油圧であろうが電気であろうが、機械は残るのです。 |
 |
|