 |
 |
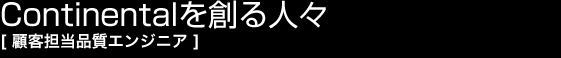 |
 |
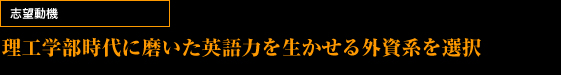 |
 |
 |
理工系学生は一般に英語を苦手とする者が多いのですが、わたしもその一人。高校時代まで英語嫌いでした。しかし大学に入学した時に一念発起。国際人として活躍するために英語を勉強したのです。そして学部3年が終了した時点でアメリカに語学留学。帰国後に4年生の時に「ヘテロエピタキシャルダイヤモンド応用の放射線センサー」を研究して論文を書き、卒業しました。
この英語能力を生かせる職場は外資系です。ただ外資ならどこでもいいというわけではありません。外資系に加えてメーカーという条件が加わります。そうして候補企業を探していた時に出会ったのがコンティネンタルでした。
まず「車」であることに興味を引かれ、面白いと思いました。でもそれだけでは強い志望動機にはなりません。決め手は面接官の言葉です。最終面接で出会った方は次のように言いました。
「きみは、日本と海外の架け橋になりたいと言った。その志はとても貴重だ。しかし働いているうちに仕事に慣れて変わってくるものだ。そんな志は忘れてしまうだろう。だがそれでいいんだよ。きみは意識しなくなるだろうけれど、きみが働くことが日本と海外の架け橋になっているのだから」。この言葉でわたしの志望は固まりました。 |
|
 |
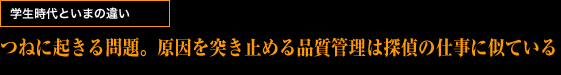 |
だれでもそうだと思いますが、わたしたちが消費者、ユーザーの立場でモノを買うとき、出来上がったモノ、結果しか認識していません。車に対してのわたしの意識もそのレベルでした。
しかしコンティネンタルで働いていくうちに、何にでも開発と生産、組立というプロセスがあり、その過程でたくさんの問題が発生し、一つ一つを解決してはじめて誕生することに気づきました。
また多くの人が、車は自動車メーカーが作っていると思っているかもしれませんが、車の60〜70%はサプライヤーの製品です。わたしたちは車メーカーのエンジニアと一緒にクルマ作りの喜びを味わうのです。
わたしはキーレスエントリーシステムを担当していますが、使っている人には簡単操作で便利なテクノロジーのひとつでしょうが、実はつねに問題が出てくるのです。いま携わっているもののひとつに4年前に量産開始になったキーレスエントリーシステムがありますが、問題がぽつぽつ出てきています。 |
 |
 |
その問題を車メーカーから連絡を受けて協議し、その結果を踏まえて解決できるようにドイツに依頼します。日本では品質エンジニアとして不具合の原因を探します。システム構成は、「キー」、ドア部にある「アンテナ」、それから「エンジンコントロールモジュール」ですが、どこの何が問題を起こしているのかは、いろんな組み合わせが考えられ、突き止めるのが大変です。比喩的に言えば探偵の仕事に似ているところがあるかもしれないですね。 |
 |
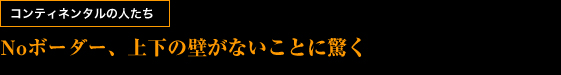 |
まだ入社1年目ですが、入社して驚いたのは上下の壁がないことです。日本企業では「偉い人は偉い」のだと思いますが、コンティネンタルの偉い人は自分が偉いと思っておらず、非常にフランクです。またチーム力がすごくて、なにか問題が起こったときの結束力はとても強いと思います。
上下関係がない、チームワークがいいことと関係しますが、わたしのような新人がわからないことを聞きに行っても、だれも嫌な顔をせずに教えてくれることにも正直言って驚きました。みなさん自分の仕事を抱えて忙しいはずなのに、例外なく親切に対応してもらえるのです。新人扱せず、対等に仕事をする、地位や部署という壁がないNoボーダーがコンティネンタルの文化なのだと思います。 |
 |
|