 |
 |
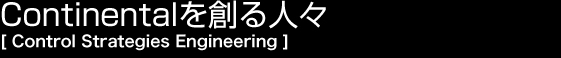 |
 |
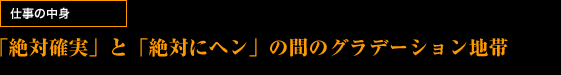 |
 |
 |
私の所属するCSEグループとは、Control Strategies Engineeringの意味。日本語では「車両統合制御グループ」です。10年くらい前までのEBS(Electric Brake System)は、ブレーキがロックしないようにするABSが主流でしたが、現在はクルマの安定性を保つスタビリティや、路面傾斜でクルマがずり落ちないようにする制御などによって、よりクルマの安全性を高めているのです。
EBSには、ABS、TCSなどがありますが、もう1つ重要なのがESC(Electric Stability Control)です。これは、急なハンドル操作時や滑りやすい路面を走行中に車両の横滑り(オーバーステアやアンダーステア)を感知すると、自動的に車両の進行方向を保つように車両を制御するシステムです。
ハンドル角、ヨーレート、旋回Gなどのセンサから車輌の状態をモニタリングし、前後左右輪にブレーキをかけたり、エンジンの出力をコントロールして、車輌の向きを修正し、横滑りを制御するものです。 |
難しいのはセンサからもらった情報をどう判断するかですね。車輌走行条件によっては、普通に走っていても、センサがあたかも横滑りをしているかのような出力をする事もあります。それを正直に実行すると危険です。逆にセンサ情報を疑い過ぎても制御システムとして成り立ちません。この情報は「絶対確実」と「絶対にヘン」という黒白がハッキリしていれば簡単ですが、その間に黒から白までの灰色のグラデーション地帯があるのです。
それをプログラムで確認、ベンチテスト、車輌走行試験を通して確認して信頼性を高めていくのです。この信頼性を私たちはロバストネス(robustness)と呼んでいます。システムの「強健さ」という言葉が一番近いニュアンスですかねえ。頼りがいのあるESCがドライバーとクルマの安全を守るのです。 |
 |
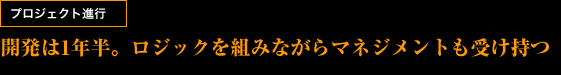 |
コンティネンタルでの1つのプロジェクトは量産開始まで2年くらいかかり、私たちの開発は1年半くらいを要します。スタートはカーメーカーの求める要求仕様の理解です。2カ月くらいをかけて仕様を検討し、それから「整合」になります。既存技術を援用できる部分、新規技術が必要な部分を切り分けていく段階です。それからABS、TCS、ESCなどのチームが分担して開発していきます。
ただ仕様理解→整合→開発→テストと一方向ではなく、整合、ベンチテスト、実車試験は必要に応じ随時行われます。
私自身はロジックを開発するプレーヤーですが、開発プロジェクトの時間と品質のマネジメントも受け持っており、野球で言えばプレイングマネジャーという役割ですかね。
|
 |
 |
|
 |
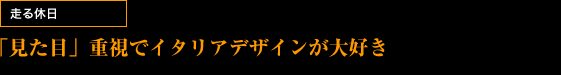 |
休日はいろいろな意味で「走って」いますね。マラソンもやりますし、自転車も、バイクでも走っています。フルマラソンの方はベストタイムが4時間半くらいですかね。自転車は、イタリアのPinarello(ピナレロ)というロードレーサー仕様に乗っていまして、佐渡島で開催される「佐渡ロングライド」という大会では130キロを走破したこともあります。オートバイはDucati (ドッカティ)。ツーリングで1日400キロは走りますね。
自転車もオートバイもイタリア製ですが、私はあくまでも「見た目」重視(笑)。そんなわけでイタリアのデザインが大好きなんですね。
その他仕事以外の活動と言えば、中学、高校とサッカー部だったということもあって、今も会社の仲間とフットサルなどをしています。体を動かすことで日ごろのストレスの発散にもなって気持ちがいいですし、特にそのあとの生ビールは最高ですしね!
皆さんが入社されたら、歓迎会でぜひ飲みましょう。 |
 |
|